

2025年7月取材
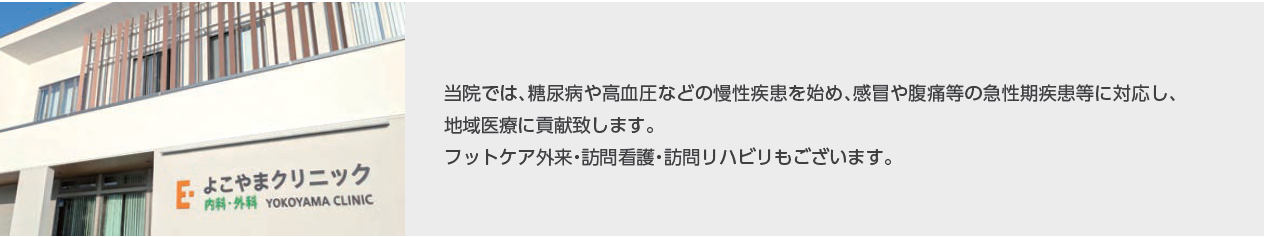

当院は2013年山形県米沢市に開院し、外来診療のほか、看取りを含めた訪問診療にも力をいれております。2019年には訪問看護事業部、2021年には訪問リハビリを開設しました。また、皮膚・排泄ケア認定看護師(WOCN)が開院当初から常勤しているため、WOC外来も併設し、WOCに関わる患者さんへの対応も行っています。訪問リハビリにおいては、G-TESを導入し、在宅療養中の利用者が自立した生活を送れるように対応しております。
当院の理念としては、地域に根差した信頼される医療を通じて、地域の皆様の健康を守り、親しみやすく信頼される医療を提供し、安心して暮らせる社会づくりに貢献します。また、専門的な知識で質の高いサービスを提供し、患者様の一人ひとりの人生に寄り添い、心の通う医療で安心と信頼を届けられるようにスタッフ一同心がけております。
横山クリニックの佐藤裕也と申します。
私は、現在、皮膚・排泄ケア認定看護師として、主に在宅訪問をしています。在宅患者さんが安心安全に暮らせるように、最大限の援助をさせていただけるよう努めています。
当院の院長が看取りも含めた在宅診療に力を入れたいという想いに共感したことが、こちらに勤務した理由になります。私と院長とは以前別の病院で一緒に勤めていて、院長がこちらのクリニックを開業される際に、是非自分も拾ってくださいとお願いして入職させていただきました。現在は、こちらで在宅医療の看護を一生懸命、そして楽しくさせていただいています。
2年前に参加した学会でG-TESを使った症例の発表を聞きまして、これは当院の訪問看護や訪問リハビリ、在宅医療でも使えるのではないかと思い、院長に相談したところ、使ってみましょうと快諾いただき導入いたしました。
当院の訪問リハビリでは週に1回、介護報酬の枠で入ることが多いのですが、やはり週1回のリハビリではなかなか患者さんのADLも上がってこないので、出来れば、ここはG-TESの力を借りて在宅患者さんの廃用の予防やADLの改善が出来たらという想いから導入いたしました。
褥瘡の患者さんにG-TESを使用した例としては、その患者さんは寝たきりの状態で全然動けない患者さんだったのですが、その方は右の大転子部に深い褥瘡を保有しており、訪問看護と訪問診療で医療処置をしていましたが、最初の処置から2か月経過したところから褥瘡の深度停滞が見られ、加えてADLも改善していない状態でした。そのタイミングでG-TESを使ってみた結果、創部の褥瘡の血流が改善して、みるみる褥瘡が治ってきまして、これはもしかしたらG-TESの効果があったのではないかと思い、現在も訪問看護と訪問診療にG-TESを使用しています。

先ほどの例のように、G-TESは廃用症候群に対してかなりアプローチができるのではないかと思っています。他の事例としても、拘縮の患者さんにG-TESを使用して、自然拘縮が治ってきたというものや、まったく寝たきりの患者さんにG-TESを使用したところ、その方が自力で起き上がれようになったという効果も出ています。
将来的にも褥瘡の患者さんは増えてくると思うのですが、これまでの使用効果も参考にして、G-TESの有用性を、G-TESを使ってどれくらいの効果があるのかということを試していきたいと思っています。
私は、当院に勤務して3年になります。その前は総合病院で6年ほど、患者さんの機能改善のリハビリを担当していました。
総合病院に入院される方は、主に怪我や病気をされた患者さんで、私としては将来的に病気や怪我をする前に、予防的な面でのリハビリをしていきたいと思っていたところ、よこやまクリニックが訪問リハビリを始めると聞き、私はこちらの院長先生と先ほどインタビューを受けた佐藤看護師とも以前から職場外での交流があったこともあり、私も是非在宅での訪問リハビリをしたいとお話させていただき、3年前より当院で訪問リハビリをしています。
私は在宅でのリハビリは初めてだったのですが、こちらについて、私は、患者さんの生活環境でリハビリができるということに関心を持っています。在宅の患者さんは、病気なども維持期に入っているので、なかなかすぐには機能の改善が難しいところはありますが、患者さんや、患者さんのご家族に寄り添って、その方々が望まれるような生活をサポートしていきたいと思っています。
私が現在介入している患者さんは、基本的に介護保険を利用されている方々で、要支援1から要介護5までの幅広い方でのリハビリの利用があるのですが、年齢でいうと、主に70代から90代の方で、脳梗塞や神経疾患などの基礎疾患や既往歴のある方が多く、歩くのが大変、外出が大変といった、生活に何かしらの支援が必要な方々なので、廃用症候群がない方はあまりいないというところです。
それぞれ筋力や体力の低下や様々な痛みなどを抱えられている方々に、廃用症候群に対しての筋力増強にG-TESをいちばん使用していて、下腿に浮腫のある方にもG-TESを使っています。浮腫に対しての基本的な内服治療となると、利尿剤などでの水分調整といったところだと思うのですが、それでもなかなか良くなられない方にG-TESを使ってみたところ、長年悩まれていた浮腫の症状が改善された事例がありましたので、患者さんの状態に合わせて周波数を選択しながらG-TESを使っています。廃用症候群の患者さんに対しては主に20ヘルツを使用しています。
リハビリの時間内でG-TESを使って良くなられる患者さんは、やはりある程度自分で動ける方になると思います。歩けるけれども痛みがある患者さんや、歩くのが大変だという方にはG-TESを使用した効果がわかりやすいのですが、G-TESをリハビリに使えるのは、1人の患者さんに対して週1回ないし2回で、それぞれ1回20分間ほどなので、G-TESはそれだけの使用時間で症状が好転するほどの魔法の機械ではないと思うので、G-TESの使用とリハビリ時間以外のセルフエクササイズや、過ごし方が大事になってきます。G-TESの即時効果の例として90代の患者さんにG-TESを使用したところ、ベッドに移動する際の歩き格好が、いつもはヨタヨタしていたのがG-TESの使用後には腰がすっと伸びていて、その効果は患者さんのご家族も感じられていました。
もうひとつ、G-TESの使用方法として、患者さんの状態維持のための使用があります。在宅の患者さんは、なかなか良くならないと悩まれる方もいらっしゃいますが、自分としては状態の維持も重要だと思っていて、状態維持にはある程度運動するなどの刺激が必要であり、患者さんの中には「このままで、何もしたくない。」とおっしゃる方もいらっしゃるのですが、何もしなければADLが低下していくばかりなので、状態維持をするためにもG-TESを使用した筋肉への負荷が必要だと考えています。また、状態維持ができている患者さんにもG-TESを使用することによって、ご自身でなんとか歩けるとか、ちょっと介助を受けながら歩けるという方もいらっしゃるので、G-TESがその維持に貢献していると、効果を感じています。
廃用症候群の患者さんで、ADLの低下により寝たきりで褥瘡を有している方がいらっしゃいまして、訪問リハビリでADLの改善していくよう医師から指示があり、その患者さんにG – T E S を導入しました。寝たままで使用できるというG-TESの利点を活かしての導入を決めたのですが、やはりその患者さんも、あまり起きたくないといった、積極的な運動療法を用いる事や体を動かすことにも抵抗感がおありでしたので、先ず、お試しでG-TESをお持ちしてみたところ、「これだったらいいよ。」と、いうことで使用を開始しました。実際にリハビリとしては、筋力増強とADLの改善を目的に入っていったのですが、以前に介入した患者さんがG-TESの使用で浮腫みが良くなったという、G-TESが血流の改善に効果があるという実感があったので、褥瘡の治癒についても創部への血流量はある程度必要にはなってくるので、G-TESは褥瘡にも効果があるのではないかと、看護師とも話して、こちらも患者さんにG-TESを導入するもうひとつの理由になりました。
G-TESを使った褥瘡への効果は、導入前は半信半疑なところではありましたけれど、実際の効果については、先ほどの佐藤看護師のお話のとおり、かなりの効果がありました。治療は、感染を起こすようなトラブルもなく順調にいって、看護師も「あれだけひどかった褥瘡が、こんなに早く良くなるってことはまずない。」と言っており、G-TESの使用は褥瘡にも効果があることがわかりました。こちらの患者さんは在宅の方でしたので、栄養状態も決して良いわけではなかったですし、入院患者のように柔軟なケアを入れられるわけではなかったのですが、そういった中でも順調に傷が良くなられていったので、そこにはG-TESの効果があったのではと考えています。
G-TESを使っていて、その有用性を感じるのは、運動をすることや体を動かすことにはちょっと抵抗感がある患者さんにも、寝たままでの使用で効果を得られるところです。G-TESを寝たままの患者さんに使用して、運動療法と同等の効果が得られるというところは、G-TESのひとつのメリットだと思います。また、難聴の患者さんや軽度認知症などの患者さんで、運動療法についての指示をうまく理解されない方にも、G-TESは一定の刺激を機械のほうでコントロールしてくれますので、本来こちらが求めている運動がうまくできない方にも十分な運動の機会を提供できていると思います。G-TESは、ベルト電極から筋肉にかなり多くの刺激が入るので、それと同等の効果を運動療法で出そうとすると、多分、少なくとも10種類の運動療法のバリエーションを混ぜていかないとG-TESと同じような刺激を与えるのは難しいと思うのですが、運動療法の指示の理解が難しい方にもG-TESを使用することで筋肉への刺激ができるというところは、とても大きなメリットだと感じています。
電気治療を受けたことのある患者さんでも、G-TESの広範囲の筋肉を同時に刺激するかたちに、最初はびっくりされる方が多いのですが、G-TESの使用を重ねていくごとにだんだんと慣れてこられて、こちらも徐々に刺激、強度も上げていっています。患者さん、皆さんがおっしゃるのはG-TESを使用した後に感
じる体の軽さですね。こちらから見ていても明らかに患者さんの動きが良くなったのがわかりますし、G-TESを使用したリハビリの後は、その日は1日、体の痛みも少なくなったと即時的な効果がわかりますし、やはり関節痛の原因は筋力低下だけでなく筋肉の硬さというところにも原因があるので、G-TESがそういったところにもアプローチ出来ているので、G-TESは、患者さんの訴えるさまざまな症状に介入できていると思います。当院はG-TESを導入して2年ぐらいになりますが、患者さんも長い方だとそれぐらいの期間、G-TESの導入時から現在も継続使用されている方がいらっしゃいますので、そういった患者さんもG-TESの導入当初に比べて動きが良くなられています。また、在宅で活動性の高くない患者さんでも、この2年間変わらない能力を維持できている事例もあり、こちらもまたG-TESの効果のひとつだと思っているので、G-TESを在宅の患者さんに導入した効果も十分にあったと実感しています。
G-TESの導入がスムーズにいけば、途中で脱落する方はいなかったのですが、スタートの時点で、G-TESの独特な電気刺激といいますか、その刺激に対して敏感な方はいらっしゃいます。G-TESを使用した電気刺激は、治療においてはある程度の強度が必要だと思いますが、その刺激に至る前の触診の段階で、筋収縮がわずかに出るか出ないかというところでダメと言われる方、こちらも1回ではやめないのですが、やはり2回ぐらいトライしても変わりのない方、疼痛の閾値が低いといいますか刺激に敏感な方には使用していませんが、スタートさえ上手くいってしまえば、そこから脱落した人は現状いません。だいたいの患者さんは、G-TESをした後の効果を実感されています。
G-TESの効果として、筋肉への刺激が筋力の増強に効果があることは勿論、そこから現在は、G-TESの刺激がもたらす筋肉の運動が糖尿病などへの効果があるなど、様々な病気に対しての効果もいろいろと検証されていると思いますが、私共は今回、G-TESの褥瘡への効果に言及をしてみて、G-TESは褥瘡の治療にも効果があるのではないかという検証結果が出ましたので、その効果の検証を継続して、G-TESの使用対象や効果の範囲がより広がってくると、こちらとしても、G-TESを使用するにあたって、こういったところにも効きますといった紹介ができると良いと思います。
現在も、私自身G-TESの効果をいろいろ調べているところで、運動の効果、免疫効果、代謝物質への効果、認知症などへの予防効果といった様々な効果がG-TESの電気刺激によって得られるのではないかと考えています。今もG-TESについていろいろな研究がされていて、これからのこととも思いますが、G-TESの使用による効果に期待しています。
やはり、私の治療対象は在宅の患者さんなので、認知症の患者さんへのG-TESの効果の可能性が広がってくると良いと思っています。すでに認知症になられている患者さんや、在宅医療に長年関わっている中で、だんだんと物忘れがひどくなってきたなと感じる方もいらっしゃり、そういった症状には内服も必要だと思いますが、G-TESの電気刺激によって今よりも体を動かすといったことが認知症予防のひとつになるのではないかと、G-TESの電気刺激による運動効果が筋力だけではなく、病気そのものへのアプローチの幅といいますか、G-TESの使用の可能性が広がってくると良いと思っています。

